
今回は東京有明医療大学の松浦 悠人先生にお話を伺った。
実家が鍼灸院でもある松浦先生は、精神科領域の研究を行っており
日々業界発展のためにご活躍されています。
今回は、松浦先生に研究者になるまでの道のりや、臨床現場に「研究」を
どう生かすのかなどをインタビューさせていただいた。
_ _ 本日はお忙しいところありがとうございます。よろしくお願いします。
まず始めに、先生がどのような経緯で研究を始めたのかをお伺いしたいと思います。
東京有明医療大学を卒業後、大学院に進学し、大学院終了後、そのまま大学に就職しました。
元々は実家が鍼灸院ということもあり、臨床家を目指して大学に入学しました。
ただ、先輩の卒業研究のお手伝いをさせてもらってから、いつの間にか研究の面白さに
ハマってしまい研究を続けています。
_ _ 現在は精神科領域が主軸だと思うのですが、最初から精神科領域の実験を行っていたのですか?
最初は精神科領域とは関係ない研究から始まりました。
大学4年時の卒業研究では脛骨神経に鍼通電刺激を行い、サーモグラフィーで計測した皮膚温がどのように変化するかを検証する実験でした。この研究は大学院の先輩の研究で、その先輩の研究を手伝いながら僕も卒業論文を書いていました。
_ _ 精神科領域の研究はいつから始まったのですか?
大学院の後期課程に入学してからです。最初は肩こりの研究で、肩こり患者の唾液ストレスホルモン(コルチゾール)を計測し、鍼治療によって唾液コルチゾール動態がどのように変化するかを研究していました。この研究を前期課程の2年間行い、後期課程に進学後から精神科の研究を始めました。
精神科領域の研究の始まり
_ _ 肩こりと精神疾患では少しジャンルが違うように思いますが、なぜ精神科領域で研究を始めることになったのでしょう?
元々精神科領域には興味がありました。
僕は東洋医学の『心身一如』の考えが好きでした。
鍼灸治療を受けることも大好きなのですが、鍼を受けることで体だけではなく、心もスッキリすることを自分の経験からも感じたことがあり、メンタルに関係しているだろうなと考えていたので研究したくなり、始めようと思いました。
博士課程に進学するタイミングの時に、僕の指導教員のところに精神科クリニックから共同研究の話があったので、そのタイミングで僕が共同研究に参加することになりました。
_ _ そして大学院後期の3年間(博士課程の期間)は精神領域の研究が始まったのですね。
そうですね。大学院後期課程に進学したのと同時に、埼玉医科大学東洋医学科に研修生として入り、2年目からは非常勤講師として働きつつ、埼玉医科大学総合医療センターの画像診断科・核医学科でMRIを用いた研究を行っていました。この研究では同院精神科の協力のもと、鍼刺激がうつ病患者の脳機能に及ぼす影響を研究しました。ですので、博士後期課程の時代は東京有明医療大学、埼玉医科大学、精神科クリニックの3つを掛け持ちでした。
_ _ とてもお忙しい3年間でしたね?!
充実していました笑
なので、2年生の時は大学には週に1回くらいしか行くことがなかったですね。
ほとんどが学外での活動でした。
その後、博士の学位を取得し、東京有明医療大学で2年間助手として務めた後に現職となりました。

1日の流れと研究の現実
_ _ 大学での勤務をされているとのことなのですが、1日の流れが
全く想像できないのですが、どのような1日をお過ごしですか?
曜日によって違うのですが、日中は授業や大学の業務があるので、朝や授業終わりに研究業務をすることが多いです。例えば、今日だと朝8時に出勤してから2時間くらいは研究関連の仕事をしてから授業を行いました。今日は授業が2コマあったので、その後は学内の仕事をして、研究関連の作業をしていました。
_ _ ”研究者”とはいえ、日中に研究をすることはほとんどないんですね?!
そうなんです。大学教員の仕事は研究だけではないので、勤務時間中は授業資料の作成や学生対応、委員会の仕事などが中心となります。また、学会関連の仕事もあります。例えば、僕は全日本鍼灸学会の臨床情報部エビデンス委員会というところに所属しているので時間ができた時には論文を読んでエビデンスをまとめたりといった仕事をしています。他には、論文を書き進めたり、文献収集をすることもあります。
_ _ 実際に研究する時間は決まっていない状態なのですか?
授業や会議、臨床など1週間のルーティンがあるので、それ以外の時間を研究業務に充てられるので、そこが研究の時間になります。ただ、実際に人に鍼を介入してデータを取るような実験研究は難しいので、そのような研究は大学院生がやってくれています。
どの大学の教員も同じだと思うのですが、被験者を集めて実験を行いデータを取ることは、授業がある期間は難しいです。春休みや夏休みのような長期休みに一気に進めることが多いのではないでしょうか。

_ _ 研究する時間が決められていて研究しているものだと思っていました。
時期にもよりますが、大学の業務が重なってくると、どうしても研究の時間が削られてしまいます。もちろん全員ではないと思いますが、このような状況に置かれている先生は多いのではないかと思います。
_ _ 1つの論文を完成させるまで、どのくらいの期間かかるのでしょうか?
研究の内容にもよるので一概には言えませんが、大学院後期課程は3年あるのですが、僕の場合、3年間で論文を仕上げるのはけっこうギリギリでした。分野にもよりますが、ヒトを対象とした臨床研究の場合、研究を立案してから論文にするまでには数年かかります。。
研究は時間と、お金と、労力が非常にかかります。
研究は患者さんへの情報提供の武器の一つ
_ _ ここまで先生の研究者への道のりを経歴を踏まえてお話して頂きました。
臨床現場と研究が全くの別物になることは良くないと思うのですが、臨床現場と研究はどのように繋がっていけると思いますか?
研究の成果を患者さんへの情報提供をする際の一つの武器として使っていただきたいです。
治療プランは、医療者が患者さんに情報を提供し、患者さんと共同で意思決定することが望ましいです。その際にリスクも含めた信頼性の高い医療情報(エビデンス)を提示し、患者さんにとって最善の治療を選択していくことが重要になります。お互いが納得した上で治療を決めた方が治療の満足度も高くなるのかなと思います。
臨床研究をやっている立場だと、このようなインフォームドコンセントの際に、患者さんへの情報提供の材料としてエビデンスを使ってほしいと思います。
基礎研究をやっている方たちからすると、メカニズムの説明に役立ててほしいなど、研究分野により少し変わってくると思います。
_ _ 臨床をしている先生の中で、論文を読んで活用している先生はどのぐらいいるのでしょうか?
それは僕も気になりますね。
全体的に見るとまだまだ少ないだろうなとは感じます。これは鍼灸師に限らず、すべての医療職でも同様の傾向だと思います。
エビデンスはあくまで物事を選択するための武器の1つだと思います。
だから、他の武器をたくさん持っている人は論文に必要性を感じないというのも一つの形ではあると感じています。
論文を読むのにもトレーニングが必要なので、それを咀嚼してわかりやすく発信しているのが学会の役割です。情報収集するには学会に参加することが手っ取り早いかもしれないですね。
_ _ 先生はこれまで研究者の道を歩まれてきたと思うのですが、
最終的には治療院で施術したいという思いはありますか?
今のところないです笑
もちろん臨床してると施術も楽しいですが、研究がやっぱり楽しいんですよね。
論文という成果ができた時がとても嬉しくて、共同研究者とする仲間がいて、その仲間と頑張っていくことが学生の時の文化祭のような感じで楽しいです。
もちろん、研究の中で知らないことをしれたりもするので面白いし、勉強できることも嬉しいです。研究は最初から最後まで楽しいです!
完成して最後に仲間と飲むビールが最高に美味しいんですよね笑
医療の手の届かないところにてを差し伸べられる職業
_ _ 最後に、インタビューしている先生に必ずこの質問をさせていただいているのですが、鍼灸師はどのような職業で、理想の鍼灸師像とはどういった鍼灸師なのか教えてください
鍼灸師は”鍼とお灸をする仕事”。同時に『医療の手の届かないところにてを差し伸べられる職業』だと思っています。そして「生まれた時から死ぬまでの患者さんに寄り添える」鍼灸師はそんな職業だと思います。そして、私にとっての理想の鍼灸師像は、この素晴らしい鍼灸治療を患者さんに提供しつつ、現場で起きている喜びや感動を世界に発信できる鍼灸師です。鍼灸の素晴らしさを広く伝えていくことは今後の世代の使命であると思います。
鍼灸師は、赤ちゃんからお年寄りまで、幅広い年齢層に対して寄り添う方法があることを知っていますが、それを鍼灸師以外がどれだけ認知しているかが大切になってきます。「鍼灸といえば、最初から最後まで面倒をみてくれる仕事」ということをもっと他の医療職や一般の方に知ってもらうために動き続けなければならないと思います。
僕自身、今は病気と診断された患者さんを対象とした臨床研究を行っていますが、今後は症状はあるけど診断には至らない方やなんとなく不調を感じている方を鍼灸研究の対象にしなければならないと感じています。東洋医学には「治未病」という言葉があるように、疾患の有無に関係なく介入できることが鍼灸の良いところですので、その特徴を科学的に証明していきたいです。

取材:Therapist Camp 元木 いお
プロフィール
松浦 悠人
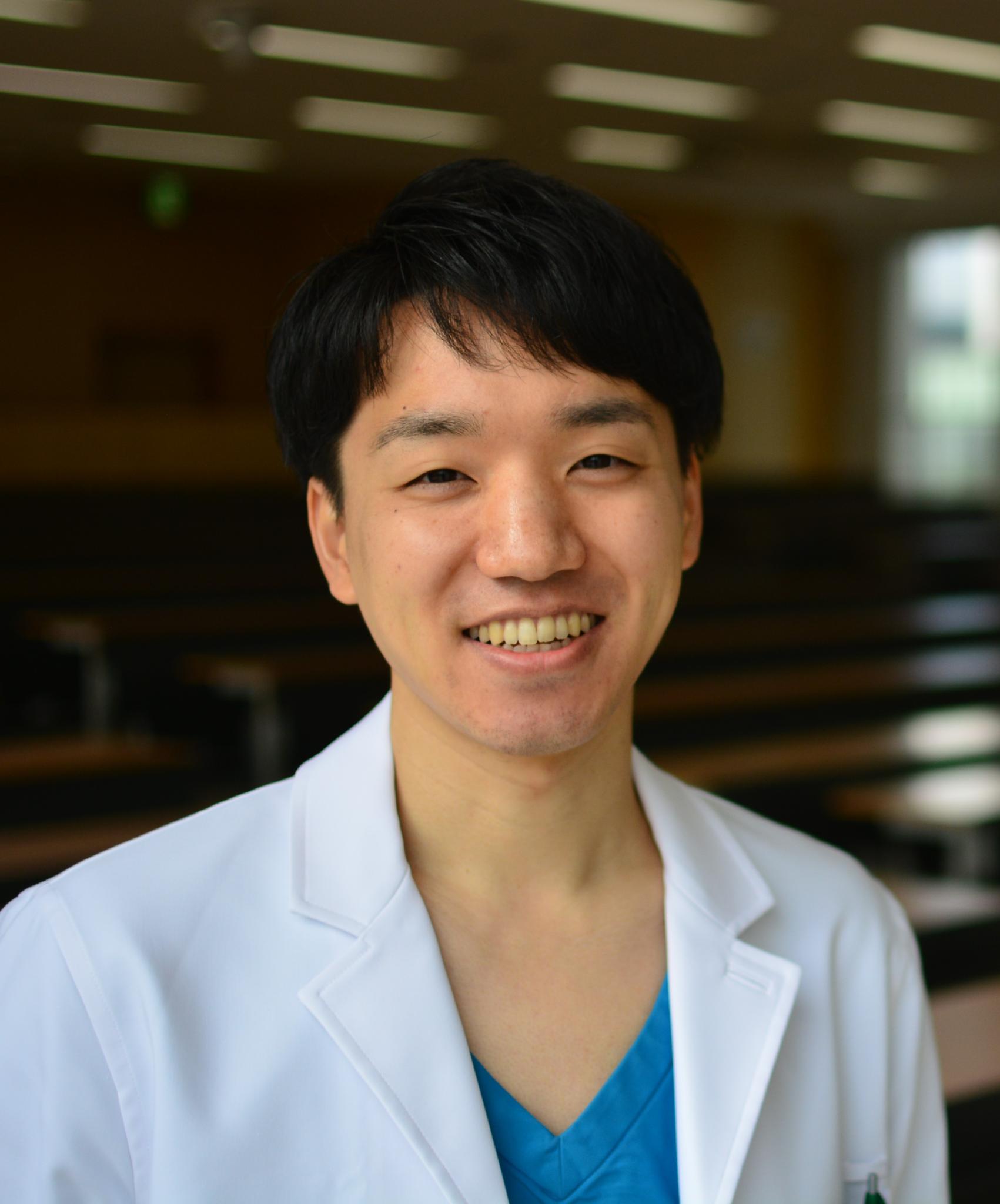
博士(鍼灸学)
東京有明医療大学 保健医療学部
鍼灸学科 助教
松浦先生プロフィール
https://researchmap.jp/matsuurayuto/
精神医療に鍼灸が活用されるための鍼灸院リストをHPで公開したい!(クラウドファンディング)
https://camp-fire.jp/projects/814611/view
SNS : X
こちらをシェアをしてみませんか?